病院でもらった処方せんを薬局に持って行ったとき、
「前の薬局より高いな」「あれ?安くなってる?」と感じたことはありませんか?
実は、同じ薬をもらっても、薬局によって支払う金額が変わることがあります。
「薬は国が値段を決めているはずなのに、どうして?」と疑問に思う方も多いはず。
今回は、その理由を生活者の目線でわかりやすく解説します。
1. 薬そのものの値段は全国共通
まず知っておきたいのは、薬そのものの値段は全国どこでも同じということ。
これは「薬価(やっか)」と呼ばれ、国が一律で定めています。
たとえば胃薬の「タケキャブ錠10mg」は1錠○○円と決まっており、どの薬局でも変わりません。
ですから「薬そのものの価格差」ではなく、調剤にかかる費用の違いが会計に影響しているのです。
2. 薬局ごとの「調剤基本料」の違い
薬局では、薬を渡すだけでなく、
- 処方せんの内容を確認する
- 飲み合わせや副作用をチェックする
- 飲み方を説明する
といった仕事が行われます。
この基本的なサービスにかかる費用が「調剤基本料」です。
この基本料は薬局の規模や条件によって変わります。
- 小規模でかかりつけに近い薬局 → 高めになることも
- 大規模チェーン薬局や処方せんの集中度が高い薬局 → 集中度が高くなれば安くなる傾向
- 病院の敷地内にある薬局→一番安いかも?
そのため、同じ薬でも薬局によって最終的な金額が違ってくるのです。
3. 薬局ごとの「加算」の有無
薬局では、患者さんの安全を守るためにさまざまな取り組みが行われています。
これが「加算」という形で費用に反映されます。
たとえば、
- かかりつけ薬剤師指導料:同じ薬剤師が継続的にサポートしてくれるとき
- 後発医薬品体制加算:ジェネリックを積極的に取り扱う薬局
- 地域支援体制加算:在宅医療や夜間対応などをしている薬局
これらが加算されると、薬代以外の部分で数十円〜数百円の差が出ることがあります。
4. 保険証や自己負担割合の違い
意外と忘れがちなのが、保険証や負担割合の違いです。
同じ薬をもらっていても、
- 3割負担の人
- 1割負担の高齢者
では、当然支払う金額が変わります。
また、公費負担(子ども医療証や難病医療など)があると、ほとんど自己負担がないケースも。
「前より高い」と思ったら、保険証の条件が変わっていないかも確認してみましょう。
5. 実際にどう選べばいい?
では、薬局をどう選べばよいのでしょうか?
- 値段を少しでも安くしたい → 調剤基本料が低めの地域密着薬局が有利なことも
(病院と同じ敷地内にある薬局は基本的に調剤基本料が低いです) - 安心・サポート重視 → かかりつけ薬剤師や在宅対応など、加算がついても手厚いサービスが受けられる薬局が安心
つまり、値段だけでなく「サービス内容とバランス」を見て選ぶことが大切です。
まとめ
- 薬そのものの値段は全国共通
- 違いが出るのは「調剤基本料」や「加算」といった薬局のサービス料
- 保険証や自己負担割合によっても変わる
- 値段だけでなく、サポート体制も考えて薬局を選ぶのが大切
「同じ薬なのになぜ違うの?」と感じたときは、
薬局で気軽に薬剤師に聞いてみてください。きっと納得できる説明をしてくれるはずです。


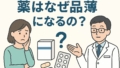
コメント