坐薬(ざやく)は、解熱や吐き気止め、便秘薬などでよく使われるお薬です。ところが、複数の坐薬が処方されたときに「どれを先に入れるの?」と迷ってしまう方も少なくありません。
今回は、坐薬を複数使うときの順番や注意点について、薬剤師の視点からわかりやすく解説します。
まず大前提:医師・薬剤師の指示が最優先
薬の使い方で最も大切なのは、処方してくれた医師や薬剤師の指示に従うことです。患者さんの症状や体格、他のお薬との兼ね合いによって、最適な順番は変わるからです。
この記事で紹介する内容はあくまで一般的な目安としてご覧ください。自己判断で順番を変えるのは避けましょう。
坐薬の種類と「基剤」の違い
坐薬には目的ごとにいろいろな種類があります。
- 解熱鎮痛薬の坐薬(発熱や痛みを抑える)
- 吐き気止めの坐薬(内服できないときに使用)
- 便秘薬の坐薬(排便を促す)
- 痔の治療薬の坐薬(炎症や痛みを抑える)
そして重要なのは「基剤(きざい)」と呼ばれる土台の部分です。坐薬は薬の成分を基剤に混ぜて固めた形をしていますが、この基剤の種類によって、体内での溶け方が変わります。
- 脂溶性基剤(例:カカオ脂など) → 体温で溶けて薬を放出する
- 水溶性基剤(例:マクロゴールなど) → 腸内の水分を吸って崩れ、薬を放出する
複数の坐薬を使うときの順番
一般的な目安としては、
水溶性基剤の坐薬を先に、脂溶性基剤の坐薬を後に
使うことが推奨されています。
理由
脂溶性基剤を先に入れてしまうと、直腸内に油膜のようなものが広がり、後から入れた水溶性基剤の溶け方や薬の吸収を妨げる可能性があります。
逆に、水溶性基剤を先に入れれば、その薬が吸収された後に脂溶性基剤を追加しても影響が少なく、両方の薬の効果がしっかり出やすいと考えられています。
使用の間隔について
同じ基剤同士なら特別な間隔をあける必要はない場合が多いですが、水溶性と脂溶性が混在する場合は30分〜1時間程度あけるのが一般的な目安です。
間隔をあけずに続けて入れてしまうと、薬が外に出てしまったり吸収が不十分になる恐れがあります。
実際の例
- ダイアップ坐薬(ジアゼパム) → 水溶性基剤
- アンヒバ/アルピニー坐薬(解熱剤) → 脂溶性基剤
このような組み合わせでは、ダイアップを先に、解熱坐薬を30分以上あけてから使うといった指導が行われることがあります。
坐薬を使うときの注意点
- 坐薬は冷蔵庫で保管し、使用直前に取り出す
- 尖っている方を先にしてゆっくり挿入する
- 使用後はしばらく横になって安静にする
- 下痢をしている場合は薬が吸収されにくいことがある
- 使い方に迷ったときは必ず薬局や医師に相談する
まとめ
- 坐薬を複数使うときは 医師・薬剤師の指示が最優先
- 一般的な目安は 水溶性基剤を先に、脂溶性基剤を後に
- 基剤が異なる場合は 30分〜1時間あけるのが望ましい
坐薬は症状を和らげるために大切なお薬です。正しい順番と使い方を守ることで、効果をしっかりと発揮させることができます。迷ったときは、かかりつけ薬局で遠慮なく相談してください。
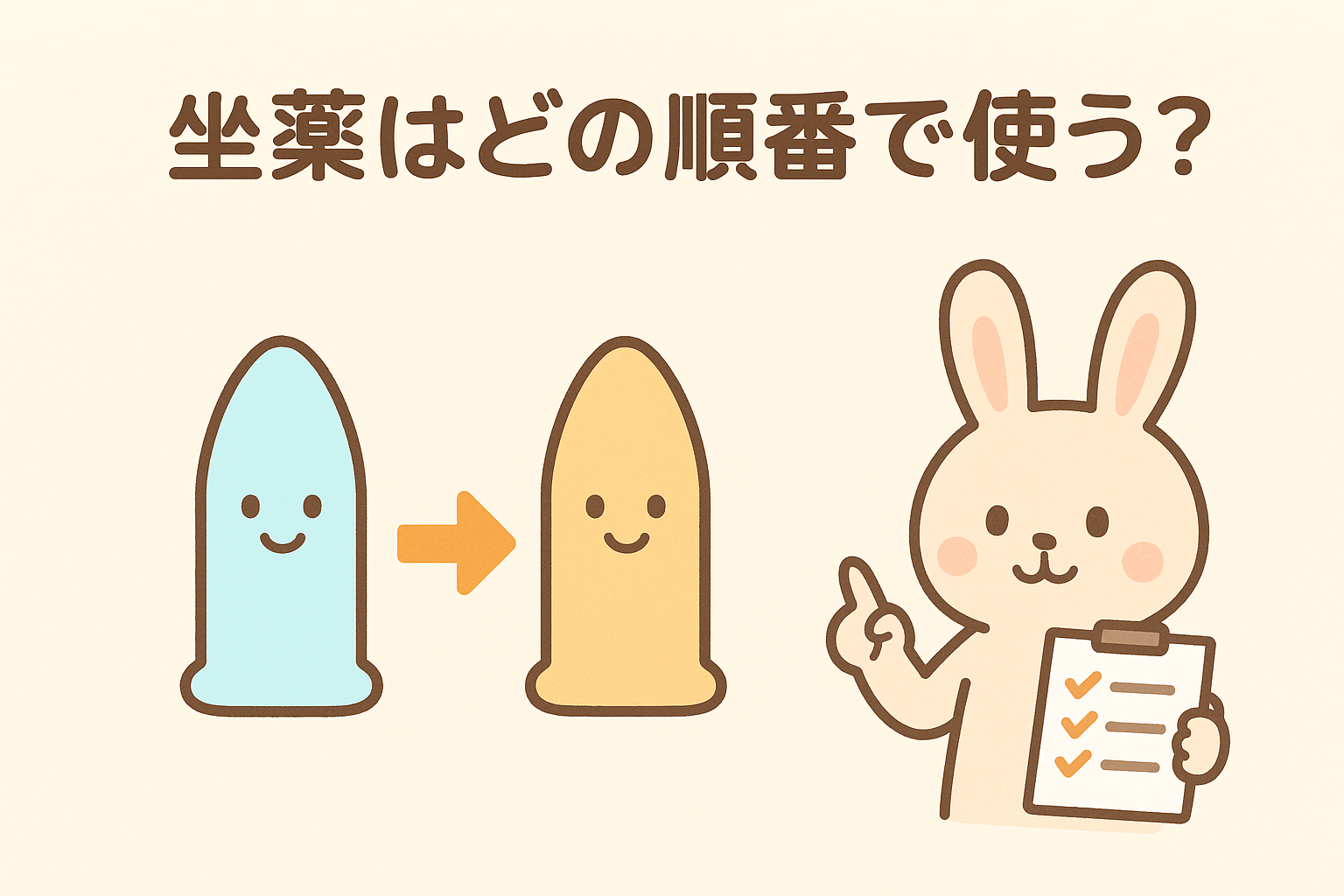

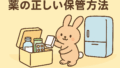
コメント