はじめに
病院でもらう処方せんを薬局に出すと、袋にきれいに小分けされた粉薬が出てきます。患者さんからは「どうやって作っているの?」「手作業で詰めてるの?」とよく聞かれることがあります。
実は、粉薬は薬剤師が専用の機械や道具を使って、一人ひとりの処方に合わせて調製しているのです。今回は、薬局の裏側で行われている粉薬作りの流れや機械について、わかりやすくご紹介します。
粉薬を作るまでの基本の流れ
- 処方せんの確認
まず医師から出された処方せんを確認します。薬の名前や量、日数を正確に読み取ることが最初のステップです。 - 薬の取り出し
薬局の棚には、多くの薬がアルファベットや五十音順に整理されています。そこから必要な粉薬や錠剤を取り出します。 - 秤量(はかりとり)
粉薬の量は非常に細かく決められています。薬剤師は「秤量器(天びん)」という精密な器具を使って、正確に計量します。
粉薬を混ぜるための道具
場合によっては、複数の薬を混ぜて服用しやすくすることもあります。そのときに活躍するのが以下の道具です。
- 乳鉢と乳棒
すり鉢とすりこぎのような形をした道具で、粉を混ぜ合わせるために使います。均一に混ざるように、丁寧にすり合わせていきます。
よくイメージされる「薬屋のひとりごと」のような感じですね。
乳鉢と乳棒が家にほしい!という方は↓

乳鉢 乳棒付 2セット60mm 90mm 磁製 スパイス 丸薬粉砕機 すり鉢 理化学実験 磁性実験用品
理化学実験からキッチン用途まで使える磁器製乳鉢セット。60mmと90mmの2サイズがセットになっており、少量から多量まで幅広く対応。衛生的で洗いやすい磁器製、精密なすり合わせ面で効率的な粉砕が可能。スパイス挽きから実験までマルチに使える実用...

1回分ごとに分ける「分包機」
患者さんに渡すときは「1回分が1袋」になっていることが多いですよね。これを実現しているのが 自動分包機 です。
- 薬剤師が必要な量を上部のホッパーに入れる
- 機械が1回分ずつ計算して小さな袋に自動で分ける
- さらに袋には日付や「朝・昼・夕」などの文字を印字できる
この分包機のおかげで、間違いを減らし、患者さんが飲み間違えないように工夫されているのです。
安全と衛生の管理
薬を正しく作るには、精度だけでなく安全や衛生管理も重要です。
- ダブルチェック:薬剤師同士で処方内容や計量を確認し合う
- 異物混入防止:調剤室は清潔に保ち、手洗いや衛生管理を徹底
- 誤差の防止:秤量器や分包機は定期的に点検・校正を行う
これらの工夫により、患者さんは安心して薬を受け取れるようになっています。
まとめ
薬局で粉薬を作る工程は、一見地味ですが「正確さと安全性」が何より大切です。
- 精密な秤量器で薬の量を正しく量る
- 乳鉢や混和機で均一に混ぜる
- 自動分包機で1回分ずつ小分けにする
- 薬剤師によるチェックと衛生管理で安全性を確保
こうした手順を経て、皆さんの手元に粉薬が届いているのです。普段はなかなか見ることができませんが、薬袋の裏には薬剤師の細やかな工夫と努力が詰まっています。
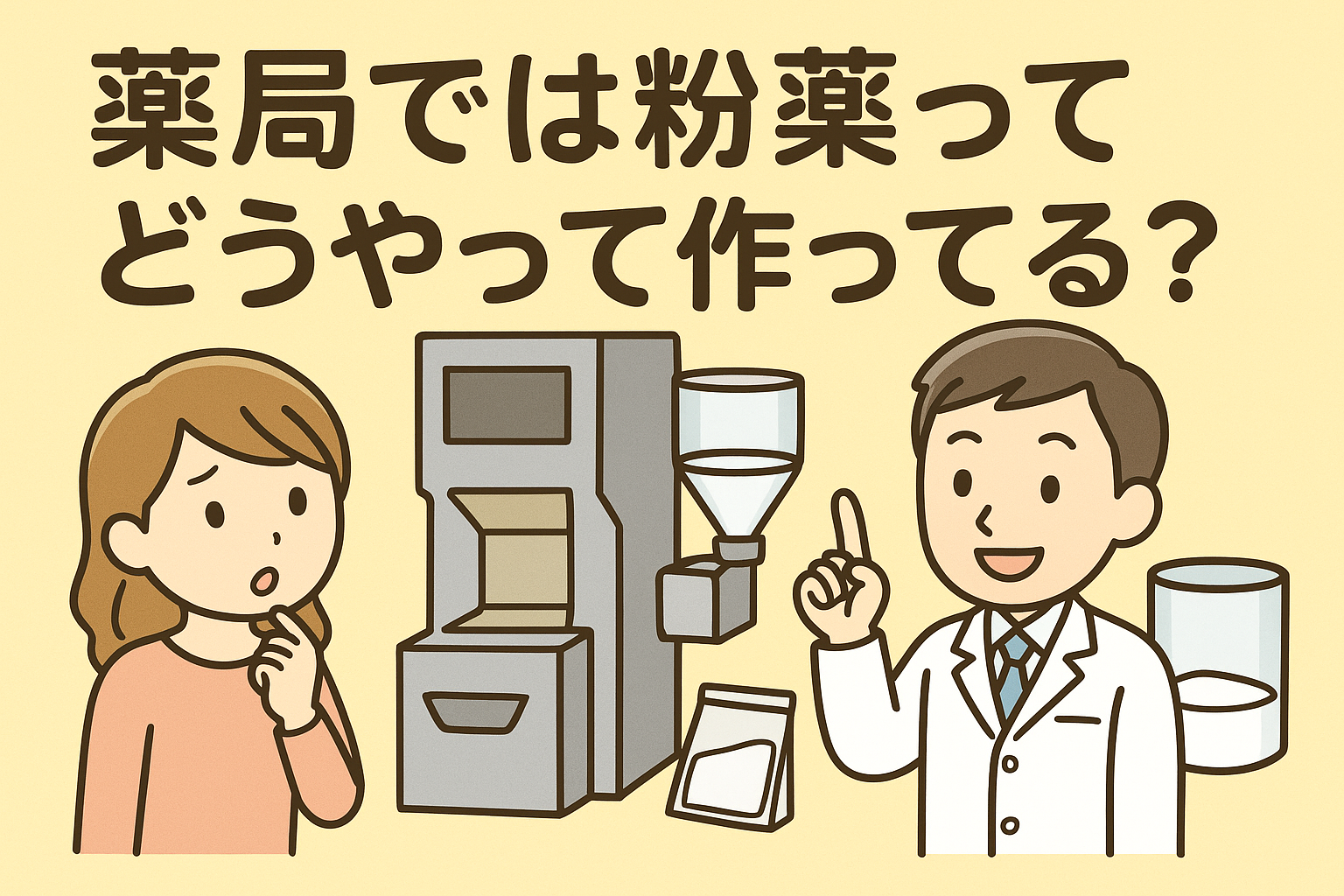

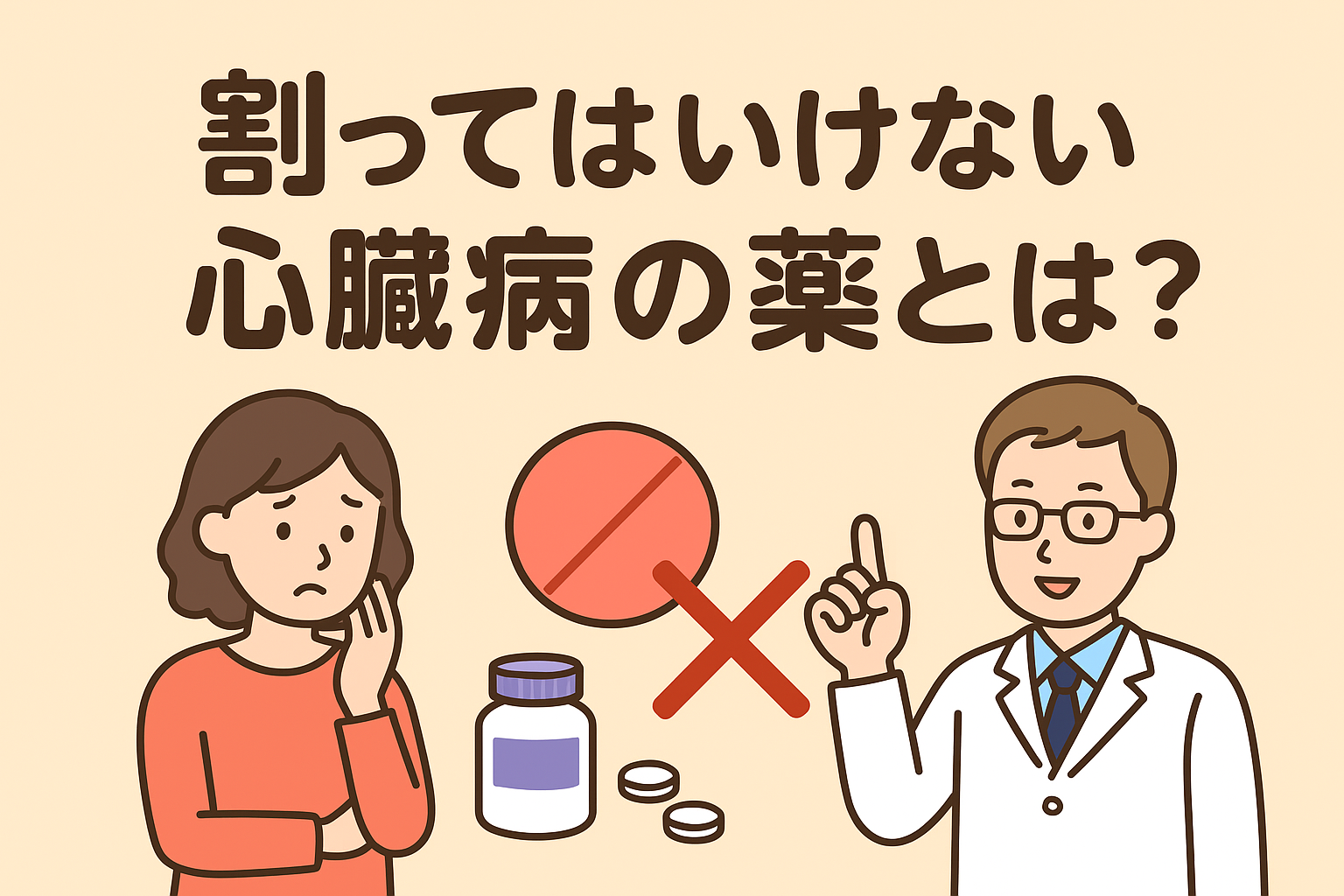
コメント